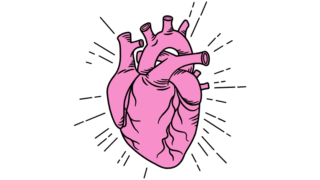お酒に強い人弱い人

こんにちは、Takamiです。
今回のテーマは、お酒に強い人・弱い人──体質と向き合うためにです。
お酒を飲んで楽しく過ごす時間は、古くから人付き合いの場として大切にされてきました。しかし一方で、「お酒に強い人」と「お酒に弱い人」がいることは、多くの人が実感しているでしょう。私自身はお酒に弱いタイプで、少量でも顔や全身が真っ赤に紅潮し、体が熱くなる感覚を覚えます。さらに、たくさん飲みたいと思えないことも特徴の一つかもしれません。飲める人たちが羨ましいと感じることもありますが、最近は「飲めない人を無理に誘わない」雰囲気が広まり、とてもありがたい時代になったと感じます。ひと昔前までは、飲めないことがからかわれたり、付き合いが悪いと見られたりすることもありましたから、大きな変化です。
では、なぜ人によってお酒に強い・弱いがあるのでしょうか。その答えは、主に遺伝、肝臓の働き、体質の違いにあります。
アルコールの代謝と酵素の働き
アルコールを飲むと、体内でまず肝臓に送られます。肝臓では「アルコール脱水素酵素(ADH)」によってアルコールが分解され、アセトアルデヒドという物質に変わります。アセトアルデヒドは毒性が強く、顔の赤みや動悸、吐き気などの不快な症状を引き起こす原因です。
次に、このアセトアルデヒドを「酢酸」という無害な物質に変える役割を担うのが、「アルデヒド脱水素酵素(ALDH)」です。このALDHの働きが強い人は、アセトアルデヒドが体内に溜まりにくく、不快な症状が出にくいため「お酒に強い人」となります。逆に、ALDHの働きが弱い、あるいは遺伝的にほとんど働かない体質の人は、アセトアルデヒドが体に残りやすく、少量でもすぐに顔が赤くなり「お酒に弱い人」となるのです。
遺伝と体質の違い
この酵素の活性は遺伝によって大きく決まります。日本人を含む東アジア人では、約4割が「ALDHが弱い」体質だといわれています。つまり、日本社会には「お酒に弱い人」が一定数存在するのです。西洋諸国と比べて、日本人に「すぐ顔が赤くなる人」が多いのは、この遺伝的背景によるものです。
また、体質の影響もあります。例えば、体格が大きく筋肉量の多い人は、体内の水分量が多いため、アルコールの濃度が薄まりやすくなります。そのため同じ量を飲んでも、体が小さい人より酔いにくい傾向があります。性別も関係しており、女性は男性よりもアルコールの分解能力が低いとされます。
強い人・弱い人、それぞれのリスク
お酒に強い人は、飲んでも不快な症状が出にくいため、ついつい飲み過ぎてしまうリスクがあります。アルコールは肝臓に大きな負担をかけるため、飲み過ぎは肝硬変や脂肪肝、さらには生活習慣病の原因となります。強い人こそ「自覚的に量をコントロールする」ことが必要です。
一方でお酒に弱い人は、少量でも強い反応が出るので、大量に飲むこと自体が難しい体質です。これはある意味で「過剰飲酒を防ぐブレーキ」と考えることもできます。ただし、顔が赤くなる人は体内にアセトアルデヒドが長く残りやすいため、食道がんや頭頸部がんのリスクが高いという研究報告もあります。そのため「無理して飲まない」「自分の体質を受け入れる」ことが、健康を守るうえで大切です。
飲めても飲めなくてもいい社会へ
かつて日本では「飲めて当たり前」「酒の席での付き合いこそが人間関係を築く場」と考えられていました。しかし今では、健康意識の高まりや価値観の多様化により、飲めない人に無理強いをする風潮は減りつつあります。ノンアルコール飲料の選択肢も増え、飲めない人も一緒に楽しめる環境が整いつつあるのは喜ばしいことです。
お酒に強いか弱いかは、単なる個性であり、優劣をつけるものではありません。大切なのは、自分の体質を知り、それに合わせて無理のない範囲で付き合うことです。強い人は「飲みすぎに注意」、弱い人は「無理して飲まない」、それぞれが自分に合ったスタイルを見つければいいのです。
まとめ
お酒の強さは、主に遺伝や肝臓の酵素の働きによって決まります。強い人は分解能力が高いためたくさん飲めますが、飲みすぎによる健康リスクがあります。弱い人は少量でも症状が出ますが、それは体質上の特徴であり、恥じる必要は全くありません。むしろ無理して飲まない姿勢が、将来の健康を守ることにつながります。
お酒に強い人も弱い人も、互いの違いを理解し尊重しながら、自分に合ったスタイルでお酒と付き合っていくことが大切です。