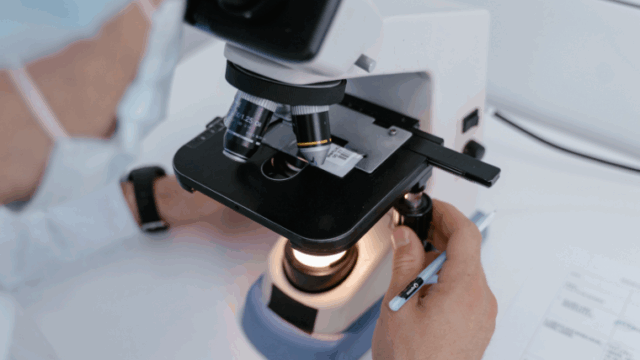診療報酬の改定と今後

こんにちは、今回テーマは、診療報酬の改定と今後です。
診療報酬とは何か
診療報酬は、病院・クリニックが保険診療で受け取る「公定価格」です。医療行為そのもの(点数)と薬価・材料価格の2つに分かれ、点数は原則2年ごとに見直されます。診療報酬の改定は、医療の質や政策目的を反映する重要な制度変更です。
最近の改定で重視されたこと
近年の改定では、働き方改革・人材確保、地域包括ケアの強化、そして医療の質向上とDX(デジタル化)推進がキーワードになっています。病床機能の見直しや入院料の再編など、医療提供体制を評価する仕組みも強化されています。これらは国の方針に基づく大きな方向性です。
診療報酬改定がクリニック経営に与える影響
改定により一部の点数は引き下げられ、別の部分で加算が設けられるといった“再配分”が起こります。結果として、診療科や診療スタイルによって増収になる医院と減収になる医院が分かれるため、経営の影響は一律ではありません。特に外来中心のクリニックでは収益構造の見直しが必要になるケースが多いです。
なぜ「安泰ではない」のか
ポイントは次の3つです。
① 政府財政と少子高齢化により医療費抑制圧力がかかること。
② 医療提供体制の評価が厳しくなり、今までの収益モデルが通用しにくくなること。
③ 物価上昇や人件費増加など外部コストの変動が診療報酬だけではカバーされにくいこと。つまり、改定があるたびに「これまで通り」が変わる可能性が高いのです。
クリニックが取りうる現実的な対策
- 収益構造の可視化(診療・検査・処方ごとの採算把握)
- 在宅医療・予防・検診など報酬体系で優遇される分野へのシフト
- 診療の効率化(予約・受付のDX化、タスク分担)
- 患者との信頼構築による受診行動の最適化(適正受診の啓発)
まとめ:変化をリスクではなく機会にする
診療報酬は今後も政策や財政状況に応じて改定され続けます。だからこそ、待つのではなく自ら動くことが重要です。採算管理、業務改善、提供サービスの見直し――これらを日常的に行っておくことが、変化の波を乗り越える最良の準備になります。
診療報酬の改定は2年ごと(点数)、薬価は原則毎年見直し。経営への影響は診療科や取り組み次第で異なるため、定期的なシミュレーションが必須です。