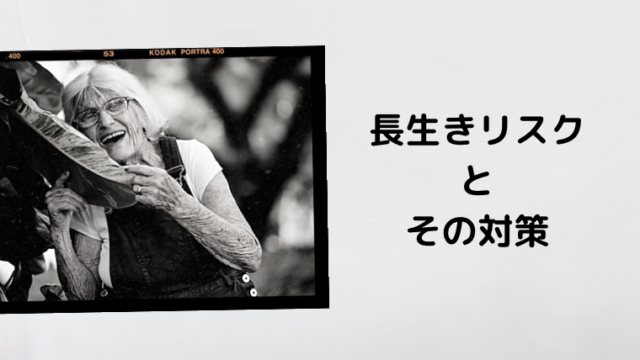お酒を飲むと眠くなるのはなぜか

こんにちは、Takamiです。
今回のテーマは、お酒を飲むと眠くなるのはなぜかです。
お酒を飲むと、ふっと眠気に襲われることはありませんか。食事の席や飲み会の後、帰りの電車で思わずうとうとしたり、布団に入る前に眠ってしまったり…。一方で、「お酒を飲まないと眠れない」という人もいるでしょう。
では、なぜお酒を飲むと眠くなるのでしょうか。そのメカニズムを解説するとともに、注意しておきたい“お酒と睡眠の関係”について見ていきましょう。
アルコールが脳に与える影響
お酒に含まれるアルコールは、体に入ると肝臓で代謝され、血液を通じて全身に運ばれます。特に大きな影響を受けるのが脳です。
アルコールは脳の神経伝達に関わる「GABA(ガンマアミノ酪酸)」という物質の働きを強めます。GABAは脳をリラックスさせ、神経の興奮を抑える役割を持っているため、アルコールを摂取すると気持ちが落ち着き、眠気を感じやすくなるのです。
また、アルコールは一時的に「セロトニン」や「アデノシン」といった眠気を促す物質の働きを高めるため、眠りやすさを感じる人もいます。これが「お酒を飲むと眠くなる」主な理由です。
眠っているようで質は低い?
お酒を飲むと寝つきが良くなることから、「寝酒(ナイトキャップ)」として利用する人も少なくありません。しかし、ここに落とし穴があります。
アルコールによる眠気はあくまで“鎮静作用”によるもので、本来の自然な眠りとは異なります。特に問題となるのが、睡眠の質の低下です。
睡眠の分断
アルコールは代謝される過程で「アセトアルデヒド」という物質を生じます。これは交感神経を刺激し、中途覚醒(夜中に目が覚める)を増やす原因となります。飲んでしばらくは眠れても、夜中に目が覚めて眠りが浅くなるのです。
レム睡眠の減少
質の高い睡眠には、脳が休むノンレム睡眠と、記憶の整理や感情の安定に役立つレム睡眠のバランスが重要です。アルコールはこのレム睡眠を抑制してしまうため、翌朝「ぐっすり寝た感じがしない」と感じることがあります。
いびきや無呼吸のリスク
アルコールには筋肉を緩める作用があり、気道の周囲の筋肉も例外ではありません。その結果、いびきがひどくなったり、睡眠時無呼吸症候群のリスクが高まることもあります。
お酒に強い・弱いで違いはある?
「自分はお酒に強いから眠くならない」という人もいるかもしれません。確かにアルコール分解の速さには個人差があり、眠気の出方も異なります。
しかし、お酒に強い人でも、実際には睡眠の質が下がっている場合がほとんどです。眠気を感じにくいからといって安心はできません。むしろ、飲みすぎて長時間浅い眠りを繰り返すリスクが高まることもあります。
「寝酒」の習慣がもたらす悪循環
眠れない夜にお酒を頼ると、一時的には眠れるように感じます。しかし、それが習慣になると次のような悪循環に陥りやすいのです。
1.寝酒で眠る
2.夜中に何度も目が覚める
3.睡眠の質が下がり、日中に眠気や疲労が残る
4.翌晩も眠れない不安から再びお酒に頼る
こうして「寝酒依存」のような状態になり、アルコール依存症のリスクも高まってしまいます。
良い眠りのためにできる工夫
お酒に頼らず眠るためには、生活習慣を見直すことが大切です。
•就寝3時間前にはお酒を控える
体内でアルコールが代謝されるまでに時間がかかるため、寝る直前の飲酒は避けることが望ましいです。
•適度な運動を取り入れる
日中に軽い運動をすることで、自然な眠気が訪れやすくなります。
•寝る前のリラックス習慣
ストレッチや読書、ぬるめのお風呂などで、自然に心身を落ち着ける工夫をしましょう。
•カフェインの摂取を控える
コーヒーやエナジードリンクは眠気を妨げるため、午後遅く以降は避けると良いです。
まとめ
お酒を飲むと眠くなるのは、アルコールが脳の働きを抑え、リラックス作用を強めるためです。しかし、それはあくまで一時的なもので、実際には睡眠の質を大きく下げてしまいます。
寝酒が習慣になると、かえって眠れない悪循環に陥るリスクもあります。
「お酒を飲むと眠れるから」と安心するのではなく、質の高い自然な睡眠を得るために、飲酒との付き合い方を見直してみてはいかがでしょうか。