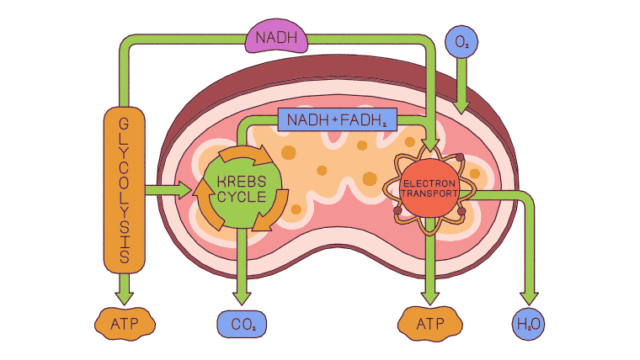厚底シューズvs薄底シューズ

こんにちは、Takamiです。
今回のテーマは、厚底シューズ vs 薄底シューズ:健康の観点から考えるメリット・デメリットです。
ランニング界や若者のファッションで注目を集めている厚底シューズ。箱根駅伝でも多くの選手が採用し、クッション性やスタイルの良さから人気が高まっています。一方で、私は学生時代から薄底シューズ派。身体本来の機能を活かし、足裏の感覚を研ぎ澄ますには、薄底シューズが優れていると感じています。
では、健康の観点から考えたときに、厚底シューズと薄底シューズはどのように使い分けるべきなのでしょうか? それぞれのメリット・デメリットを整理しながら、どんな場面でどちらを選ぶべきかを考えてみます。
厚底シューズのメリット・デメリット
メリット
① クッション性が高く、衝撃を吸収してくれる
厚底シューズの最大の特徴は、ミッドソールの厚みとクッション性の高さです。着地時の衝撃を和らげ、膝や足首への負担を軽減します。特に、長距離ランナーや関節に不安を抱える人にとっては、大きなメリットです。
② 推進力が得られやすい
近年の厚底シューズには、カーボンプレートなどのテクノロジーが搭載されており、蹴り出しのエネルギーを効率よく推進力に変えることができます。そのため、スピードを求めるランナーにも人気があります。
③ 長時間歩いても疲れにくい
ランニングだけでなく、普段のウォーキングや立ち仕事にも向いています。足裏への負担を減らし、長時間歩いても疲れにくいというメリットがあります。
デメリット
① 足の筋力が鍛えられにくい
クッション性が高いぶん、足の裏やふくらはぎの筋肉を使う機会が減ります。そのため、足のアーチが弱くなるリスクや、長期的に見て筋力低下につながる可能性があります。
② 足裏の感覚が鈍くなる
厚底シューズは、地面との接地感が薄いため、足裏の感覚が鈍くなりやすいです。特に裸足感覚を重視するスポーツ(たとえば剣道や体操)をしている人にとっては、感覚を養いにくくなる点がデメリットになります。
③ 不安定になりやすい
ソールが厚くなることで重心が高くなり、バランスを崩しやすくなります。特に、不整地やトレイルランニングでは足首を捻るリスクが高まるため注意が必要です。
薄底シューズのメリット・デメリット
メリット
① 足裏の感覚が鋭くなる
薄底シューズは、地面との距離が近いため、足裏の感覚が研ぎ澄まされます。裸足に近い状態で歩くことで、バランス感覚や体の使い方が向上しやすくなります。
② 足の筋力を鍛えられる
クッションに頼らずに走ることで、足の指や足裏の筋肉が自然に鍛えられます。これにより、足のアーチが崩れにくく、外反母趾や扁平足の予防にもつながります。
③ 身体の自然な動きを引き出せる
厚底シューズに比べて、膝や足首の関節の動きを自然に使いやすくなります。本来の身体の機能を活かして走る・歩くことができるのは、大きなメリットです。
デメリット
① 衝撃がダイレクトに伝わる
クッションが少ないため、着地の衝撃が直接足に伝わります。特に、膝や腰に負担がかかりやすい人にとっては、怪我のリスクが高まる可能性があります。
② 長距離やスピードを出すには向かない
厚底シューズに比べて推進力が少なく、スピードを求めるランナーには向いていません。また、長距離を走ると足の疲労が溜まりやすいです。
③ 路面の影響を受けやすい
薄底のため、小石やアスファルトの凹凸をダイレクトに感じます。そのため、長時間歩くと足の裏が痛くなることもあります。
健康の観点から考える「使い分けのポイント」
① 目的に応じて選ぶ
•長距離ランや膝の負担を減らしたい場合 → 厚底シューズ
•足の感覚を鍛えたり、筋力を強化したい場合 → 薄底シューズ
② 徐々に切り替える
普段厚底シューズを履いている人が、いきなり薄底シューズに変えると、足の負担が大きくなります。逆も同じで、薄底シューズに慣れている人が厚底シューズを履くと、感覚の違いに戸惑うことがあります。少しずつ慣らしながら使い分けることが重要です。
③ 両方をバランスよく使う
健康のためには、どちらか一方に偏るのではなく、シチュエーションに応じて両方を取り入れることがベストです。例えば、日常のウォーキングでは薄底シューズ、ランニングでは厚底シューズといった形で使い分けるのもおすすめです。
まとめ
厚底シューズと薄底シューズには、それぞれ異なるメリット・デメリットがあります。どちらが優れているかではなく、「目的や自分の身体に合ったものを選ぶこと」が大切です。
•膝の負担を減らし、スピードを求めるなら厚底シューズ
•足裏の感覚を鍛え、自然な走りを求めるなら薄底シューズ
ぜひ、ライフスタイルやトレーニング内容に合わせて、賢く使い分けてみてください!