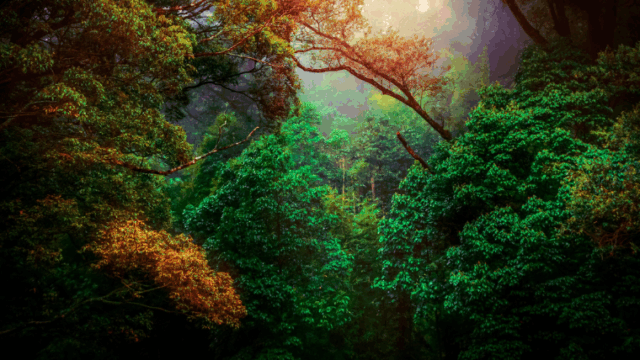脂肪細胞にも記憶はあるか

こんにちは、Takamiです。
今回のテーマは、脂肪細胞にも“記憶”はあるのか?──身体が覚えている「肥満の履歴」です。
「マッスルメモリー」という言葉を聞いたことがある方も多いでしょう。これは、過去に鍛えていた筋肉が、再びトレーニングを始めたときに、比較的早く元に戻る現象を指します。つまり、筋肉にはある種の“記憶”があるのです。
↓まだ読んでない人はぜひチェックしてみてください
マッスルメモリーは存在するか
では、「脂肪細胞」にも同じような“メモリー”が存在するのでしょうか?
今回は、最新の研究を交えながら「脂肪細胞の記憶」について考えてみたいと思います。
一度太った人は、痩せても“戻りやすい”
ダイエットを経験したことがある人の多くが、「リバウンド」の苦しさを知っているはずです。どれだけ体重を落としても、時間が経つと、なぜか元に戻ってしまう。これは単に「意志の弱さ」や「運動不足」だけでは説明がつかない現象です。
実は、一度太ったことのある人の体内では、脂肪細胞そのものが“肥満状態”を記憶している可能性があるのです。
脂肪細胞の数は増えて減らない
人の脂肪細胞には大きく2つの特徴があります。
1.脂肪細胞は大きくなったり小さくなったりするが、数はあまり減らない
2.一度増えた脂肪細胞の数は、基本的に減らない(除去されない)
つまり、太って脂肪細胞の数が増えると、仮にダイエットで体重を落としても、それらの脂肪細胞は体内に“残り続ける”のです。
これらの脂肪細胞は、小さくなったとしても、「再び脂肪を蓄えたい」という働きを活性化させやすい状態になっており、体内のホルモンや代謝にも影響を与えます。
脂肪細胞が「脳」に指令を出している?
脂肪細胞は単なるエネルギーの貯蔵庫ではありません。
実は、ホルモンを分泌する“内分泌器官”の一つでもあります。
中でも重要なのが「レプチン」というホルモン。これは、脳の視床下部に作用し、「食欲を抑える」信号を送る働きがあります。ところが、太って脂肪細胞が増えすぎると、このレプチンの働きが鈍くなり、いわゆる“レプチン抵抗性”が起こると考えられています。
この状態になると、脳は「まだ十分にエネルギーが足りていない」と誤解し、食欲を増進させる信号を出すようになります。
ここで注目すべきなのは、脂肪細胞が“過去の肥満状態”を覚えていて、それを維持しようとしているかのような反応をするという点です。これが「脂肪細胞メモリー」という仮説につながります。
最新の研究でも明らかに?
脂肪細胞の“記憶”に関する研究は、まだ発展途上ではあるものの、以下のような知見が出てきています。
•肥満を経験したマウスの脂肪細胞を別のマウスに移植すると、そのマウスも太りやすくなる
•脂肪細胞はエピジェネティクス(DNAのスイッチ)によって、「過去の状態」を保持しやすい
つまり、肥満という状態が、脂肪細胞レベルで“記憶”として体内に残る可能性が、科学的にも示唆されているのです。
身体の記憶は優れているが、厄介でもある
筋肉の記憶は「良い意味」で働きます。再び鍛えれば早く元に戻れるからです。
しかし、脂肪細胞の記憶は「厄介な記憶」とも言えるかもしれません。一度太った身体は、それを“標準”とみなし、それを維持しようとする傾向があります。
この記憶は、生存本能とも関係していると考えられています。飢餓に備え、エネルギーを確保しようとする“進化の記憶”とも言えるかもしれません。
だからこそ、太りにくい生活習慣を
脂肪細胞の記憶があると仮定すれば、「太らないこと」が一番の予防になります。
もしすでにダイエットを経験しているなら、リバウンドしにくい生活習慣を継続することがカギです。急激な食事制限ではなく、適度な運動とバランスのとれた食生活を心がける。体重ではなく「体脂肪率」や「筋肉量」に意識を向ける。
「記憶された脂肪」に惑わされず、今のあなたの状態が“新しい標準”になるよう、身体にじっくり覚え込ませていきましょう。
まとめ
•脂肪細胞にも“過去の肥満状態”を記憶している可能性がある
•一度太ると、脂肪細胞が減らず、肥満を維持しやすい状態になる
•ホルモンの作用によって、脂肪細胞は脳に影響を与えることもある
•ダイエット後のリバウンドを防ぐには、継続的な生活習慣の改善が必要
脂肪細胞の“メモリー”は、決してオカルトではなく、科学的にも少しずつ裏付けが進んでいます。身体の声に耳を傾けながら、少しずつ“新しい自分”を定着させていきましょう。