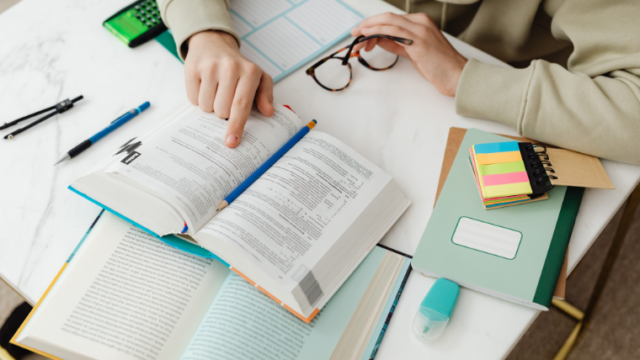子どもの頃から本に触れる効果

こんにちは、Takamiです。
今回のテーマは、子どもの頃から本に触れる効果——紙の本のぬくもりと知の土台づくりです。
はじめに
タブレット端末が身近になり、どこでも気軽に絵本や児童書が読めるようになった現代。たしかに便利な時代です。けれど、僕個人としてはまだまだ“紙の本”の力を信じています。特に子どもたちにとっては、ページをめくる音や手触り、表紙のデザインなど、五感を通して記憶に残る「本の体験」がとても大切に思えるのです。
わが家では、できるだけ子どもたちを図書館に連れていくようにしています。自分で好きな本を選んで、夢中になって読んでいる姿を見ると、「読書って、ただ知識を得るだけじゃないな」と実感します。本に親しむことは、子どもの内面を豊かにし、将来にわたって大きな財産になる。今回は、そんな「子どもの頃から本に触れることの効果」について、国内外の研究も交えながらご紹介したいと思います。
語彙力・表現力が自然と育つ
読書によって最も顕著に育まれるのは「語彙力」です。日常会話では出会わないような言葉や表現にも、本を通して出会うことができます。カナダのトロント大学が行った研究によれば、幼児期に読み聞かせを多く受けた子どもは、同年代の子と比べて語彙の発達が早く、その後の学力にも良い影響を与えることが分かっています。
また、語彙だけでなく「表現力」も鍛えられます。登場人物のセリフや感情の描写を読むことで、相手の気持ちを想像したり、自分の気持ちを言葉で表現する力が養われます。こうした「ことばの筋力」は、作文や発表の場だけでなく、日常生活でも大きな武器になります。
想像力・共感力を高める
本を読むという行為は、文字から情景を思い浮かべる「想像の訓練」でもあります。テレビやYouTubeのように映像で提供される情報と違い、本は“読者の頭の中で完成する世界”。特に絵本や物語を通して、子どもたちはさまざまな状況や価値観に出会い、想像力を深めていきます。
米国のエモリー大学の研究によると、物語に没頭することで、実際に脳の共感に関わる領域が活性化されるという結果が出ています。
これはつまり、「本を読むことで、他人の立場に立って物事を考える力=共感力が育つ」ということ。いじめやトラブルを未然に防ぐ社会的スキルとしても、非常に重要な力です。
集中力と内的な安定感を養う
本を読む時間は、スマホやゲームと違い、静かで落ち着いた時間です。ページをめくりながら物語の世界に浸ることで、自然と集中力が高まり、心が整います。特に紙の本には、通知も広告もありません。集中を妨げるものが少なく、「自分だけの世界に没入できる時間」を持てる点で優れていると感じます。
さらに、毎日少しずつ本に触れることで、「静かな時間」を楽しむ感覚も育ちます。これは、日々情報に追われる大人にとっても見習いたい習慣かもしれません。
学びに対する好奇心が育つ
図鑑、科学絵本、歴史マンガなど、ジャンルを問わずいろいろな本に触れることで、「知ることの楽しさ」を体感できます。好奇心は学びの原動力。その芽を子どものうちに育てることができれば、学校の勉強も「やらされるもの」ではなく、「もっと知りたいからやるもの」に変わっていきます。
英国の教育専門誌『Educational Research』では、「家庭で読書習慣がある子どもは、学力テストのスコアが平均より高く、学年が上がるほど差が広がる傾向がある」というデータも紹介されています。読書は一見地味ですが、実は未来の自信や学力の土台を静かに築いているのです。
紙の本ならではのメリットも
最後に、やはり「紙の本だからこそ得られるもの」もあると感じています。
たとえば:
•ページをめくる動作が楽しい
•表紙や背表紙で「お気に入り」を覚えられる
•読み終えた本を並べて達成感を感じられる
•親子で同じ本を一緒に読むとき、自然と会話が生まれる
長旅では電子書籍も便利ですが、家の中や図書館ではやはり紙の本のぬくもりが、子どもたちの読書体験をより深いものにしてくれているように思います。
おわりに
本を読むことは、「知識」や「言葉の力」を育むだけでなく、心の成長にもつながる大切な営みです。親が本を読む姿を見せること、図書館に一緒に行くこと、毎晩の読み聞かせ——そのすべてが、子どもたちの未来へのプレゼントになります。
忙しい日々の中でも、ほんの10分でもいい。本に触れる時間を、ぜひ家族の習慣として取り入れてみてはいかがでしょうか。