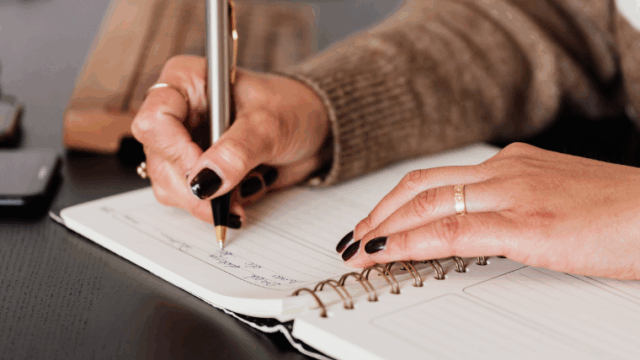教育における優しさとは何か

こんにちは、Takamiです。
今回のテーマは、教育における優しさとは何かです。
はじめに
教育の場において「優しさ」とは何を意味するのでしょうか。人に何かを教えたり、伝えたりするとき、熱心になればなるほど声を荒げたり、厳しく指導したりしてしまう場面は少なくありません。特に日本の部活動などでは、かつて体罰や過度な叱責が教育の一環のように扱われた時代もありました。しかし、これは教育ではなく指導する側の自己満足に過ぎず、決して正しい方法ではありません。
一方で、どんな場面でも丁寧に、優しい言葉をかけながら指導する人もいます。相手を尊重し、できる限り寄り添おうとするその姿勢は素晴らしいものです。しかし、ここで考えるべきは「優しさ」とは単なる甘さや過保護ではない、という点です。本当の優しさは「相手が自分の力で成長できるようにすること」ではないでしょうか。
全てを教えることは優しさか
優しいつもりで一から十まで丁寧に教えることがあります。答えをすぐに与えれば、学習者は迷わずに正解にたどり着けるでしょう。しかし、それは一時的な安心感を与えるだけで、思考力や問題解決力は育ちません。たとえば算数の問題で、答えの出し方をすべて説明してしまえば、子どもは「なるほど」と思いながらも、自分で考える経験を失ってしまいます。
教育における優しさとは、ただ「分かりやすく教える」ことではなく、「自分の頭で考える機会を与える」ことでもあるはずです。すぐに答えを与えることは、実は優しさに見えて学びの芽を摘んでしまう可能性があるのです。
ヒントを与える優しさ
では、逆に「答えを一切教えない」ことが正しいのでしょうか。もちろんそれも極端です。答えが全く見えない状態では、学習者はただ混乱し、意欲を失ってしまうかもしれません。そこで必要になるのが「ヒントを与える優しさ」です。
ヒントとは、相手が自力で答えに近づける道しるべです。たとえば、「この問題を解くときは前に習った公式を思い出してみよう」とか、「別の角度から考えるとどうだろう」という声かけがそれにあたります。直接答えを渡すのではなく、自分で気づける余地を残す。これは相手の可能性を信じ、成長の過程を大切にする態度です。
このバランスこそが教育における「優しさ」ではないでしょうか。
厳しさと優しさの両立
教育の場では「優しさ」と「厳しさ」は対立する概念のように扱われがちですが、実際には両立が必要です。本当に相手のためを思うなら、ときには厳しいことを伝える勇気も求められます。例えば「今の取り組み方では成長できない」と指摘することは、言う側にとっても苦しいことです。しかし、見て見ぬふりをする方がよほど不親切かもしれません。
ただし重要なのは、厳しさが「愛情」と「期待」に裏打ちされているかどうかです。人格を否定するのではなく、行動や努力の仕方に焦点を当ててフィードバックする。それができて初めて、厳しさもまた優しさへと変わるのです。
私が教育する立場なら
もし私が教育する立場に立ったなら、次の三つを意識したいと思います。
1.相手の可能性を信じること
すぐに答えを与えるのではなく、「あなたならできる」と信じて考える時間を与える。
2.適切なヒントを与えること
完全に放置するのではなく、考えるための道筋を示す。小さな成功体験を積ませる。
3.愛情ある厳しさを持つこと
本当に成長を願うなら、耳に痛いことも誠実に伝える。ただし必ず相手を尊重し、行動や姿勢に焦点をあてる。
教育の現場は一つとして同じ状況はありません。だからこそ、答えを一律に決めることはできませんが、「この人にどうすれば自分の力を伸ばしてもらえるか」を常に考えることが、教育者に求められる優しさではないかと思います。
おわりに
教育における優しさとは、単なる甘さでも、ただの厳しさでもありません。相手の成長を第一に考え、そのために必要な支援を与えることです。ときにヒントを出し、ときに見守り、ときに厳しく伝える。そのすべてが「優しさ」としてつながっていきます。
私たち一人ひとりが「相手の未来のために、いまどんな言葉をかけるべきか」と問い続けること。その姿勢こそが、教育における真の優しさなのだと思います。